software engineering product quality JISX0129-1 ― 2009/03/11 22:59
き し し こ ほ い !
less money means fatter ― 2009/03/11 23:47
【金がなくなるというのは太るってことだね】
British is currently officially in recession. A recession may have all kinds of effects on people, including the obvious effects such as people losing their jobs or being unable to find works, but it's also having an effect on what we eat.
People are cutting down on spending because they need to save money.
So as people cut down on spending, they are also changing what they eat and eating less healty food.
A study in Calfornia has concluded that when poverty rates increase by 10%, obesity rates also go up 6%.
A western world - nowadays less money means fatter.
from bbclearnigenglish.com
British is currently officially in recession. A recession may have all kinds of effects on people, including the obvious effects such as people losing their jobs or being unable to find works, but it's also having an effect on what we eat.
People are cutting down on spending because they need to save money.
So as people cut down on spending, they are also changing what they eat and eating less healty food.
A study in Calfornia has concluded that when poverty rates increase by 10%, obesity rates also go up 6%.
A western world - nowadays less money means fatter.
from bbclearnigenglish.com
i got short change ― 2009/03/12 12:50

【お釣りはもらったけれど・・・】
まさしく junk food, less healthy food だけれど、安いからと、マクドでホットドッグを買った。 recession の影響は私の財布にもきている。
500円出し、釣り銭を右手で受け握ったまま、列を離れ端で商品を待つ。釣り銭を握ったままポケットに入れようとした、が、その前にふと右手を開くと、百円玉2,十円玉3、だった。50円玉が1つ足りない。
クレームつけようと思ったが、ポケットに手を入れたよね、といわれるかもしれないと思って弱気になった。
1日の集計をして50円売上げが多かったらそれは私のだからね => マクドナルド大門店様
問題:釣り銭のクレームはどこまで有効か?
1) 受け取った瞬間
2) 釣り銭をポケットに入れるまで(レジを離れてもOK)
3) レシートがあればいつでも
たぶん監視カメラで記録しているだろうから、島崎弁護士に聞くまでもなく、 2) が正解だと思います。
I bought a hot dog this morning in McDonald and I gave a 500-yen coin to counter staff. I received the change by the right hand and waited for a hot dog in the corner.
When I was going to pocket it, I had a glanse at the change in my hand. There were 2 pieces of 100-yen coin, 3 pieces of 10-yen coin, that is, I got short change.
(skip the rest)
まさしく junk food, less healthy food だけれど、安いからと、マクドでホットドッグを買った。 recession の影響は私の財布にもきている。
500円出し、釣り銭を右手で受け握ったまま、列を離れ端で商品を待つ。釣り銭を握ったままポケットに入れようとした、が、その前にふと右手を開くと、百円玉2,十円玉3、だった。50円玉が1つ足りない。
クレームつけようと思ったが、ポケットに手を入れたよね、といわれるかもしれないと思って弱気になった。
1日の集計をして50円売上げが多かったらそれは私のだからね => マクドナルド大門店様
問題:釣り銭のクレームはどこまで有効か?
1) 受け取った瞬間
2) 釣り銭をポケットに入れるまで(レジを離れてもOK)
3) レシートがあればいつでも
たぶん監視カメラで記録しているだろうから、島崎弁護士に聞くまでもなく、 2) が正解だと思います。
I bought a hot dog this morning in McDonald and I gave a 500-yen coin to counter staff. I received the change by the right hand and waited for a hot dog in the corner.
When I was going to pocket it, I had a glanse at the change in my hand. There were 2 pieces of 100-yen coin, 3 pieces of 10-yen coin, that is, I got short change.
(skip the rest)
where have all the dogs gone ? ( 1 of 2 ) ― 2009/03/12 23:24
【犬はどこへいった? 1/2】
一昔前、社会インフラ系ITシステムの仕様書作りチームの末席にいた。某コンサル会社が手が足りないから助けて、というので出かけたのだが、そこには先にメーカから出向のSさんがいて、コンサルの担当者とSさんがユーザ打ち合わせに出かけ、帰ってくると、Sさんと私が打ち合わせ結果を複数の仕様書に反映させていた。
初めて仕様書を見たとき、ある機能の名称がどれもみな”・・・ドグ”となっていたのに驚いた。これはタイプミスに違いないと気を利かして小さな「ツ」を書き入れておいた。翌日、Sさん達が本日分の打ち合わせから帰り、さあ本日分を修正しようとしてファイルを開くと不思議なことに、昨日の「ッ」がなくなっている。私は今回分の反映と同時にまた小さな「ツ」を書き入れておいた。・・・ こんなことが4回か5回か続いた後、ついにSさんが叫んだ!
「ばかやろ~、ドグをなんでドッグと書くんだあ、それじゃ犬だろう」
私は目が白黒白黒となった・・・
(続きは明日)
問題:ペットを飼うのが好きか嫌いか聞いたところ、「好き」と答えた人の割合は?
a) 34%
b) 68%
c) 96%
総理府 動物愛護に関する世論調査 平成12年 より
一昔前、社会インフラ系ITシステムの仕様書作りチームの末席にいた。某コンサル会社が手が足りないから助けて、というので出かけたのだが、そこには先にメーカから出向のSさんがいて、コンサルの担当者とSさんがユーザ打ち合わせに出かけ、帰ってくると、Sさんと私が打ち合わせ結果を複数の仕様書に反映させていた。
初めて仕様書を見たとき、ある機能の名称がどれもみな”・・・ドグ”となっていたのに驚いた。これはタイプミスに違いないと気を利かして小さな「ツ」を書き入れておいた。翌日、Sさん達が本日分の打ち合わせから帰り、さあ本日分を修正しようとしてファイルを開くと不思議なことに、昨日の「ッ」がなくなっている。私は今回分の反映と同時にまた小さな「ツ」を書き入れておいた。・・・ こんなことが4回か5回か続いた後、ついにSさんが叫んだ!
「ばかやろ~、ドグをなんでドッグと書くんだあ、それじゃ犬だろう」
私は目が白黒白黒となった・・・
(続きは明日)
問題:ペットを飼うのが好きか嫌いか聞いたところ、「好き」と答えた人の割合は?
a) 34%
b) 68%
c) 96%
総理府 動物愛護に関する世論調査 平成12年 より
where have all the dogs gone ? ( 2 of 2 ) ― 2009/03/13 12:51
【犬はどこへいった? 2/2】
「ばかやろう、ドグをなんでドッグと書くんだあ!何度も何度も!」、私は目が白黒白黒となった・・・
なるほど、私が修正した部分をまた元に戻していたんですね。
私は丁寧に、
この機能の名称は、英語の watch dog (番犬)からきていること、dog を口で言うなら、”ドグ”と言っても、”ド~グ”と言っても、”ドグウ”と言っても好きにすればいいが、日本語の文章で書くなら”ドッグ”でなけれは格好がつかない、と説明した。
Sさんは、えっ、そういう意味~ぃ、それなら「 ドッグ」だね、とあっけなく言った。
Sさんは機能としての”ウォッチドッグ”の意味はきちんとわかっていたのだけれど,本を読んで学んだのではなく耳学問の人だったんだね。
【耳学問】 Weblio英和・和英辞典 http://ejje.weblio.jp/ より
knowledge picked up by listening to others without real study
英語には「耳学問」という単語はないみたいです。
「ばかやろう、ドグをなんでドッグと書くんだあ!何度も何度も!」、私は目が白黒白黒となった・・・
なるほど、私が修正した部分をまた元に戻していたんですね。
私は丁寧に、
この機能の名称は、英語の watch dog (番犬)からきていること、dog を口で言うなら、”ドグ”と言っても、”ド~グ”と言っても、”ドグウ”と言っても好きにすればいいが、日本語の文章で書くなら”ドッグ”でなけれは格好がつかない、と説明した。
Sさんは、えっ、そういう意味~ぃ、それなら「 ドッグ」だね、とあっけなく言った。
Sさんは機能としての”ウォッチドッグ”の意味はきちんとわかっていたのだけれど,本を読んで学んだのではなく耳学問の人だったんだね。
【耳学問】 Weblio英和・和英辞典 http://ejje.weblio.jp/ より
knowledge picked up by listening to others without real study
英語には「耳学問」という単語はないみたいです。
a wish made on a falling star comes true ― 2009/03/14 21:02

【星に願いを】
イラストレータの田中ひろみさんがマイコミジャーナルに、「女巡礼一人旅! 仏像好きが行く四国八十八カ所」という記事を連載している。現在24番札所まで来たようだ。
https://news.mynavi.jp/article/ohenro-1/
私の郷里は四国なのでお遍路さんには特別な思いがあるので書いておきたい。
私の生家はお遍路道からは少し離れた地区にあり、子供時代(1960年代)には、巡礼道を間違えたと思えるお遍路さんが時々家の前を歩いている程度だった。
私は、実は、お遍路さんにはいいイメージはない。お遍路さんのことを地区の方言で”ヘンド”と呼んでいた。漢字でどう書くかは知らないが、蔑称だったと思う。例えば、子供が泣きやまないとき、「ヘンドにやるぞ!」と大人は脅すのである、すると大抵の子供は泣きやむ。子供達がいたずらすると大人は「ヘンドが来たぞ!」と脅すのである、大抵の子ども達は蜘蛛の子を散らすように右往左往するのであった。だから、”ヘンド”は怖いものであった。恐ろしいものであった。
ある時、ヘンドがうちの前に来て、突然お経をあげだした。母はお礼に首からかけている袋に米か麦をいれてやるのである。それがないときは茶碗にご飯をよそって食べさせてやるのであった。この後、母は茶碗を割って捨てた。箸をどうしたかは記憶にはない。先にも言ったように遍路道からは離れたところなので私の記憶ではほんの数回のことである。
私の母は信心深い人であったから、この風景は実に不思議であった。この風景は私の心にずっと謎として残っていた。
20代半ばの頃だったか、NHKで、空海の密教には魔力があると信じられていた、というような番組があった。この時、いままでの謎が氷解した。
昔々の巡礼は病持ちが大半であった。不治の病の治癒を弘法大師の魔力にすがったのである。イメージとしては、映画「砂の器」の本浦親子のようだったのだと思う。
私の地区で、ヘンドに飯をふるまった後、茶碗を割って捨てたのは永い時の記憶というものだろう。
ところが最近の情報では、遍路宿というものがあり、お遍路さんにいろいろと接待する施設、いわばお遍路さんの民宿のようなものがあるということである。このあたりが、私のような記憶を持つ者には解せない話なのである。
田中ひろみさんにはぜひ、遍路宿の歴史など、ほんとうに昔からあったのかなど、ご報告いただければうれしい。
私の実家に以前、天保年号が記された金剛杖があった。弥七というご先祖様が巡礼に使ったものらしいが、どんな願いを持って旅したかは伝わっていない。
問題:H11年8月の内閣府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」で、この1年くらいの間に、観光、レクレーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行した者に、誰と行ったか聞いたところ、”一人”と答えた者の割合は?
a) 3.0 %
b) 36.1 %
c) 44.2 %
イラストレータの田中ひろみさんがマイコミジャーナルに、「女巡礼一人旅! 仏像好きが行く四国八十八カ所」という記事を連載している。現在24番札所まで来たようだ。
https://news.mynavi.jp/article/ohenro-1/
私の郷里は四国なのでお遍路さんには特別な思いがあるので書いておきたい。
私の生家はお遍路道からは少し離れた地区にあり、子供時代(1960年代)には、巡礼道を間違えたと思えるお遍路さんが時々家の前を歩いている程度だった。
私は、実は、お遍路さんにはいいイメージはない。お遍路さんのことを地区の方言で”ヘンド”と呼んでいた。漢字でどう書くかは知らないが、蔑称だったと思う。例えば、子供が泣きやまないとき、「ヘンドにやるぞ!」と大人は脅すのである、すると大抵の子供は泣きやむ。子供達がいたずらすると大人は「ヘンドが来たぞ!」と脅すのである、大抵の子ども達は蜘蛛の子を散らすように右往左往するのであった。だから、”ヘンド”は怖いものであった。恐ろしいものであった。
ある時、ヘンドがうちの前に来て、突然お経をあげだした。母はお礼に首からかけている袋に米か麦をいれてやるのである。それがないときは茶碗にご飯をよそって食べさせてやるのであった。この後、母は茶碗を割って捨てた。箸をどうしたかは記憶にはない。先にも言ったように遍路道からは離れたところなので私の記憶ではほんの数回のことである。
私の母は信心深い人であったから、この風景は実に不思議であった。この風景は私の心にずっと謎として残っていた。
20代半ばの頃だったか、NHKで、空海の密教には魔力があると信じられていた、というような番組があった。この時、いままでの謎が氷解した。
昔々の巡礼は病持ちが大半であった。不治の病の治癒を弘法大師の魔力にすがったのである。イメージとしては、映画「砂の器」の本浦親子のようだったのだと思う。
私の地区で、ヘンドに飯をふるまった後、茶碗を割って捨てたのは永い時の記憶というものだろう。
ところが最近の情報では、遍路宿というものがあり、お遍路さんにいろいろと接待する施設、いわばお遍路さんの民宿のようなものがあるということである。このあたりが、私のような記憶を持つ者には解せない話なのである。
田中ひろみさんにはぜひ、遍路宿の歴史など、ほんとうに昔からあったのかなど、ご報告いただければうれしい。
私の実家に以前、天保年号が記された金剛杖があった。弥七というご先祖様が巡礼に使ったものらしいが、どんな願いを持って旅したかは伝わっていない。
問題:H11年8月の内閣府「余暇時間の活用と旅行に関する世論調査」で、この1年くらいの間に、観光、レクレーション、スポーツなどのための1泊以上の国内旅行した者に、誰と行ったか聞いたところ、”一人”と答えた者の割合は?
a) 3.0 %
b) 36.1 %
c) 44.2 %
the healthy life is a wish of all ― 2009/03/15 23:27
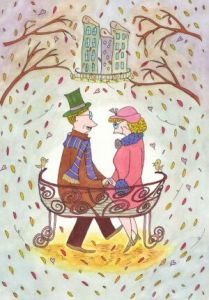
【健康はみんなの願い】
朝日新聞2009年3月15日の読書欄に、作家・早坂暁氏の書評が載っていた。ここでとりあげたのは氏が薦める本の話ではない。記事のなかにあった、氏の病気の話である。
「50歳のとき、突如として病気の集中豪雨に襲われた。心筋梗塞、胃潰瘍、膵臓炎、胆石、大腸ポリーブ群などなど。・・・・。さて、胃は全摘してもらい、心臓は半分が壊死しているから、・・・・手術をすることになったが、直前に胆嚢に癌が発生していることがわかった。」とあった。
早坂氏は、Wikipedia によれば1929年生まれとあるから、本年80歳になる。このような病歴を持ちながら30年も活躍していることになる。
50代半ばの私などにはまったく心強い話だと思ったので忘れないように記録しておきます。
イラストは、ホッターマーガレットさんの作品です。マーガレットさんの作品を見ると、とても穏やかで平和な気分になります。以下のページからご覧下さい。
http://hottermarguerite.blog120.fc2.com/
問題:平成20年6月の内閣府世論調査で、今後の生活のみとおしをたずねたところ、「これからよくなってゆく」と答えた人の割合は?
a) 7.4 %
b) 36.9 %
c) 53.7 %
朝日新聞2009年3月15日の読書欄に、作家・早坂暁氏の書評が載っていた。ここでとりあげたのは氏が薦める本の話ではない。記事のなかにあった、氏の病気の話である。
「50歳のとき、突如として病気の集中豪雨に襲われた。心筋梗塞、胃潰瘍、膵臓炎、胆石、大腸ポリーブ群などなど。・・・・。さて、胃は全摘してもらい、心臓は半分が壊死しているから、・・・・手術をすることになったが、直前に胆嚢に癌が発生していることがわかった。」とあった。
早坂氏は、Wikipedia によれば1929年生まれとあるから、本年80歳になる。このような病歴を持ちながら30年も活躍していることになる。
50代半ばの私などにはまったく心強い話だと思ったので忘れないように記録しておきます。
イラストは、ホッターマーガレットさんの作品です。マーガレットさんの作品を見ると、とても穏やかで平和な気分になります。以下のページからご覧下さい。
http://hottermarguerite.blog120.fc2.com/
問題:平成20年6月の内閣府世論調査で、今後の生活のみとおしをたずねたところ、「これからよくなってゆく」と答えた人の割合は?
a) 7.4 %
b) 36.9 %
c) 53.7 %
step by step ― 2009/03/16 23:39
【一歩、一歩】
さて、毎日、書き続けることはなかなか難しいぞ。とりあえずは1週間を目標にしよう。本日のところは決意表明を述べて終わりにします。
By the way, it is very difficult to make an essay every day.
Let me just say that I have got a long day tomorrow.
さて、毎日、書き続けることはなかなか難しいぞ。とりあえずは1週間を目標にしよう。本日のところは決意表明を述べて終わりにします。
By the way, it is very difficult to make an essay every day.
Let me just say that I have got a long day tomorrow.
i am a cookee ― 2009/03/17 23:24

【僕、食べる人】 ?
レビューアとレビューイという用語がある。システム開発ではよく使う言葉である。
レビューする人:レビューア reviewer
レビューされる人:レビューイ reviewee
ふと、辞書で調べたくなって、ネット辞書(複数)で検索したが、reviewee がでてこない。 -ie, -ey, 等々、いろいろやったがダメである。
和製英語かな?と思ったので、サンフランシスコでソフト会社を経営しているエドさんにメールでたずねたら、以下のような返事がきた。
和製英語にあらず。辞書にはないが立派な英語である。
なんでも動詞に er をつけたら ”する人”になり、 ee をつけたら”される人”になる。これはもう法則のようなものといってもいい。歌う人 singer に対して、singee という言葉もある。
ということだった。なるほど、動詞の数ほどあるのでいちいち辞書に載せてはおられないというわけですね。こういうことはもう現地に住んでいないとわかないよなあ。
昔々、日本語は漢字があるから造語は簡単だが、英語ではそうはいかないぞ、というようなことを教えられたような気がするが、どうもこれはうそだったようだ。
以前、”わたし作る人”、”ぼく食べる人”というコマーシャルがあったが、これを +er+ee の法則で作ってみると、案外これが難しい。
cook という単語は”料理を作る、料理する”という動詞だから、cooker が”わたし作る人”で、cookee が”ぼく食べる人”でいいのかなと思ったけれど、cook だけで料理人の意味があるようだし、cooker は料理道具の意味で人の意味はないようだ。
これもやっぱり、現地人のエドさんにお尋ねしないと、わからない。
イラストは、”男の料理教室”、ホッターマーガレットさんの作品です。
http://hottermarguerite.blog120.fc2.com/
レビューアとレビューイという用語がある。システム開発ではよく使う言葉である。
レビューする人:レビューア reviewer
レビューされる人:レビューイ reviewee
ふと、辞書で調べたくなって、ネット辞書(複数)で検索したが、reviewee がでてこない。 -ie, -ey, 等々、いろいろやったがダメである。
和製英語かな?と思ったので、サンフランシスコでソフト会社を経営しているエドさんにメールでたずねたら、以下のような返事がきた。
和製英語にあらず。辞書にはないが立派な英語である。
なんでも動詞に er をつけたら ”する人”になり、 ee をつけたら”される人”になる。これはもう法則のようなものといってもいい。歌う人 singer に対して、singee という言葉もある。
ということだった。なるほど、動詞の数ほどあるのでいちいち辞書に載せてはおられないというわけですね。こういうことはもう現地に住んでいないとわかないよなあ。
昔々、日本語は漢字があるから造語は簡単だが、英語ではそうはいかないぞ、というようなことを教えられたような気がするが、どうもこれはうそだったようだ。
以前、”わたし作る人”、”ぼく食べる人”というコマーシャルがあったが、これを +er+ee の法則で作ってみると、案外これが難しい。
cook という単語は”料理を作る、料理する”という動詞だから、cooker が”わたし作る人”で、cookee が”ぼく食べる人”でいいのかなと思ったけれど、cook だけで料理人の意味があるようだし、cooker は料理道具の意味で人の意味はないようだ。
これもやっぱり、現地人のエドさんにお尋ねしないと、わからない。
イラストは、”男の料理教室”、ホッターマーガレットさんの作品です。
http://hottermarguerite.blog120.fc2.com/
japanese culture, that is not all the raw fish ― 2009/03/18 22:05
【日本の文化はサシミだけじゃないぞ】
浴衣の話だが、まあ、いいでしょう。冬に水着のキャンペーンガールの発表があるくらいだし、夏までまっていたら、せっかく表にでてきた記憶がまた深い闇の底に沈んでしまいかねない。
もう30年ほど前になろうか、TBSラジオに久米宏の面白い番組があった。久米宏ともうひとりの女性が視聴者からきたいろいろな疑問・質問、もちろん愉快な質問ばかり、に対して、その道のきちんとしたしかるべきところに、その場から直接電話して答えてもらうという生放送の番組だった。
あるとき、視聴者の質問に、「ゆかたの両脇は縫ってなくて開いてますよね、それって男が手を入れるために開いているって聞いたのですが、本当でしょうか」という質問があった。
久米宏と女性は、電話帳をくりながら、どこで聞くのがいいか、相談して、”全日本浴衣着付教室組合連合会”というようなところに電話した。
リンリン
団体職員(女性)、以下女職員と呼ぶ 「はいはい」
久米宏 「TBSの久米宏と申します」
女職員 「はいはい」
久米宏 「ゆかたのことで質問があるんですけど・・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「ゆかたのぉ、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「両脇ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「開いてますよね、縫ってなくて・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「それわぁ、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「男性がですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「手を入れるために、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「開けているって、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「本当ですか」
女職員 「本当です」
なんのためらいもなく即答されたこの”本当です”に対して、”彼女いない歴・思春期以来ずう~っと男”は鼻血とめまいでその後の話は何も記憶にないのであった。
司馬遼太郎ならば、”それが、日本の文化、というものにちがいない”というところだろう。
その後、ほどなく、”彼女いない歴・思春期以来ずっと男”は一人の女性と交際し、結婚に至るのであるが、残念ながらこの放送をいまのいままで一度も思い出さなかったため、この日本の文化の恩恵には一度もあずかっていないのである。
浴衣の話だが、まあ、いいでしょう。冬に水着のキャンペーンガールの発表があるくらいだし、夏までまっていたら、せっかく表にでてきた記憶がまた深い闇の底に沈んでしまいかねない。
もう30年ほど前になろうか、TBSラジオに久米宏の面白い番組があった。久米宏ともうひとりの女性が視聴者からきたいろいろな疑問・質問、もちろん愉快な質問ばかり、に対して、その道のきちんとしたしかるべきところに、その場から直接電話して答えてもらうという生放送の番組だった。
あるとき、視聴者の質問に、「ゆかたの両脇は縫ってなくて開いてますよね、それって男が手を入れるために開いているって聞いたのですが、本当でしょうか」という質問があった。
久米宏と女性は、電話帳をくりながら、どこで聞くのがいいか、相談して、”全日本浴衣着付教室組合連合会”というようなところに電話した。
リンリン
団体職員(女性)、以下女職員と呼ぶ 「はいはい」
久米宏 「TBSの久米宏と申します」
女職員 「はいはい」
久米宏 「ゆかたのことで質問があるんですけど・・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「ゆかたのぉ、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「両脇ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「開いてますよね、縫ってなくて・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「それわぁ、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「男性がですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「手を入れるために、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「開けているって、ですね・・」
女職員 「はいはい」
久米宏 「本当ですか」
女職員 「本当です」
なんのためらいもなく即答されたこの”本当です”に対して、”彼女いない歴・思春期以来ずう~っと男”は鼻血とめまいでその後の話は何も記憶にないのであった。
司馬遼太郎ならば、”それが、日本の文化、というものにちがいない”というところだろう。
その後、ほどなく、”彼女いない歴・思春期以来ずっと男”は一人の女性と交際し、結婚に至るのであるが、残念ながらこの放送をいまのいままで一度も思い出さなかったため、この日本の文化の恩恵には一度もあずかっていないのである。



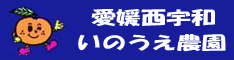
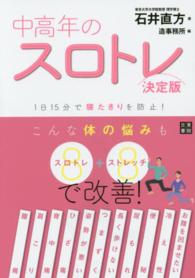
最近のコメント